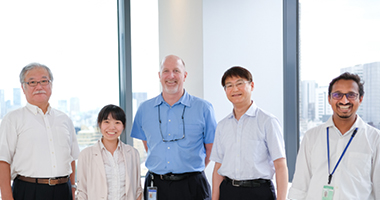業界が変わるビジネストレンド
Connected Industriesが目指す日本のものづくり
──製造業が取り組むデジタルトランスフォーメーションの現在
AIやIoTなどのICTを活用して、ヒト、モノ、コトをデジタル化することで、ビジネスモデルやビジネスプロセス、また社会のあり方をも変えていくデジタルトランスフォーメーションが新たな潮流として注目されている。製造業にフォーカスすると、ものづくりの現場を変革する「つながる工場」と、製品や機器をIoTでモニタリングすることで新たな付加価値創造やビジネスに発展させる「つながる製品」という、二つのベクトルが浮き彫りになる。「つながる工場」と「つながる製品」、この二つの方向性の現状、そして目指す方向について、それぞれの最前線に立つ二人に話を聞いた。
IoT化のキーワードは「オープン化」、そして「つながる」
ビジネス現場でIoT(Internet of Things)を語る時、個々の企業の取り組みとしてだけでなく、国の政策、つまりマクロ的な視点で俯瞰する必要がある。例えば、ドイツでは国家戦略として「インダストリー4.0」を掲げ、生産システム領域でのIoT活用に積極的だ。アメリカでは「IIC(インダストリアル・インターネット・コンソーシアム)」を発足させ、IoTの産業実装を進め、サービス領域を中心に急展開させている。
世界の潮流から導かれる、製造業がIoT化するキーワードは「オープン化」、そして「つながる」だと、法政大学デザイン工学部システムデザイン学科の西岡 靖之教授は指摘する。これはそのまま日本の製造業の課題でもあるという。
「日本の製造業の強みは現場の”人”にあります。勤勉で技術レベルが高く、目の前の課題を克服するためにひたすら汗を流し、創意工夫する人がいるからこそ、高品質な日本のものづくりは世界をリードしてきました。ただ強みと弱みは表裏一体であり、IoT化を進める際、人に起因する現場の強さが足かせにもなります」
現場が強く、自分たちのやり方と技術に自信を持っているため、欧米のようにトップダウンでのIoT化を受け入れにくい、というのが一点。現場ごとの独立意識が高いため、ある現場でIoT化を進めても部分最適で止まってしまい、全体最適に至りにくいという指摘もある。つまり「オープン化」、「つながる」がなじみにくい土壌ともいえるのだ。

一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ理事長
西岡 靖之 氏
では、どうすれば日本の製造業のIoT化が進み、生産性と競争力を高めることができるのか。つながる工場の実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加するIVI(インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ)を2015年に発足し、理事長も務める西岡教授は、「部門間、企業間の壁を越え、全体のつながりを見直す必要があります」と語る。ドイツの「インダストリー4.0」でも提唱されている「つながる工場」は、サプライチェーンの川上から川下までを構成する企業が、企業や国の壁を越えてつながることによって、生産効率や品質管理の精度をさらに向上させていこうという取り組みだ。
日本の製造業の強みを生かす「ゆるやかな標準」
「海外企業とのビジネスを継続していくためには、これからは異なる企業間の工場をつなぐという世界の潮流にも対応していかなくてはなりません。しかしそのまま日本に持ち込んで画一的に標準化していこうとしてもうまく根付きません。日本の製造業が培ってきた技術や現場の匠の知恵をすべてオープンにして標準化してしまうと、人を中心に進化してきた日本のものづくりの強みが失われてしまう危険もあります」
必要なのは、日本のものづくりの強みを活かせる「つながり方」だ。その実現に向けて、IVIが提示するのが「ゆるやかな標準」という考え方である。内容はシンプルで、工場をつなぐ場合、例えば熟練工の経験で得たノウハウや、匠の技などの現場の強みは競争領域としてつながずに独自に継承し、磨き上げていく。一方で、企業間で共通する領域は協調領域として相互に連携を図る。
「現場が強い日本の製造業の特性に合わせた進め方です。IVIに加盟している企業で議論し、協調領域をオープン化。加盟企業が社内の仕組みに取り入れ、そこで得られた成功事例を共有しながら、日本型のリファレンスモデル(つながる工場の考え方の基本モデル)を構築していく場を提供したいと思っています」

日本の製造業が覇権を握る可能性も大いにある
その成果が、2016年12月に公開した、日本のものづくりの強みを織り込んだスマート工場の基本モデル「IVRA(Industrial Value Chain Reference Architecture)」である。ドイツとアメリカが先行して、リファレンスモデルを提案しているが、コンセプト先行の印象が強い。対して、「IVRA」は具体的な人の作業などを反映する「現場感覚」が特徴だ。人の力を最大化することで現場力を高め、成長を続けてきた日本のものづくりの価値を反映させたリファレンスモデルは、海外からも強い関心を示されている。今後、IoTでつながる世界のスマート工場の枠組みづくりに近づけたいと、西岡教授は語る。
「製造業のIoTに関して、BtoBの領域ではまだどこが覇権を握るかわかりません。これまではドイツ、アメリカが先行していましたが、今後、日本のリファレンスモデルが受け入れられ、日本の製造業がトップランナーとして牽引する未来も大いにあるでしょう」
西岡教授は最後に、「自社の強みとして頑張って守るべき競争領域と、協調しても良い領域を見つめ直すにあたっては、今までの慣習を越えて考える必要もある」と強調する。「これまでこだわってきた領域が、顧客にはどのようなメリットを与えているのか?と言う顧客の視点で考えてみると、一歩上の視点で全体のつながりを考えることができるようになるでしょう」とアドバイスをいただいた。

「つながる製品」を牽引するのは、徹底した顧客視点であった
それでは「顧客の課題解決」「顧客の視点」を明確なターゲットに設定しながら、製造業のIoT化を進めてきた事例にふれていこう。労働集約型の土木建築現場でもデジタルトランスフォーメーションのもたらす変化が起ころうとしている。その最前線に立つのが、建設機械売上規模国内1位、世界2位のコマツ(小松製作所)。IoT化の成功例に挙げられることも多く、その取り組みは示唆に富んでいる。
前述したIVIの示すモデルが「つながる工場」なら、コマツの事例は「つながる製品」といえるだろう。そもそもの始まりは、1998年にサービスを開始したKOMTRAX。建設機械の情報を遠隔で確認するシステムで、きっかけは盗難防止だった。スマートコンストラクション推進本部長の四家 千佳史氏は語る。
「建機と双方向コミュニケーションを取ることで位置情報を把握し、盗難を防止する。始まりはそこでしたが、広い工事現場でもすぐに位置がわかれば故障などのトラブルの時に、お客さまの作業の中断を最小限に済ませることができ、また稼働時間や燃料消費のデータを反映して、コストダウンにつながる効率的な運用も可能になります」

スマートコンストラクション推進本部本部長
四家 千佳史 氏
顧客の課題解決を目指す取り組みから生まれた「つながる製品」
2001年から標準搭載されているKOMTRAXは、エンジンの無駄がけを防ぐ、最適な部品交換時期をアドバイスするなど、新たなビジネスモデルを提案していった。だたし、四家氏は「初めにIoTありきだったわけではない」ことを強調する。目標を達成するための手段が「たまたまIoTだった」からだ。目標とは顧客の課題解決であり、利益の最大化、深刻な人員不足の解消がそれにあたる。
メーカーとして、開発した建機の品質には絶対の自信を持っている。以前は「コマツの建機を使ってもらうこと」が顧客の利益に貢献すると考えていた。しかし顧客の立場で考えてみると、コマツの建機が関与しているのは、工事全体のプロセスから見ればごく一部にすぎない。顧客の満足度をより高めるには、建設現場全体の把握とプロセスの可視化が必要になると、考えを進化させていった。この視点に立って、新たな価値を提案するために取り組んできたのが「スマートコンストラクション」というソリューションである。
基盤としたのはクラウドプラットフォームのKomConnect。ドローンを使った測量、ICT建機に備えたセンサーやカメラなどのデータを収集し、現場の正確な3次元データを作成。どこで、どれだけの土がトラックに積まれ、どれだけの時間をかけて、どこに運ばれたのかなど、工事全体のプロセスをIoTで可視化することで、ボトルネックの場所を把握し最適な工事プロセスのプランを提示できるようになる。建機の操作も、データをもとにした自動制御が可能で、経験の少ないオペレーターでも正確な操作が可能になり、作業効率の向上につながる。実際、スマートコンストラクションの導入で生産性を3倍に高めた現場もある。

現場全体を可視化することで、「未来の現場」が実現する
「日本の土木建築の現場が構造的に抱える課題の一つが深刻な労働力不足。2025年には建設技能労働者の3分の1が不足するといわれるほどで、お客さまと共にこの深刻な課題に取り組むのは、コマツの使命でもあります。スマートコンストラクションが目指すスマートな現場は、経験が少なくても操作できるICT建機、システムで構成され、若い世代や女性たちが就業する垣根を下げる狙いもあります」
現場で実務を担当する建設会社の94%は中小企業であり、これまでは労働力不足、高齢化により「仕事があっても受注できない」と嘆くところも多かったという。従業員5人の会社が、スマートコンストラクションによって「未来の現場」を実現したことで状況が一変。若い社員、女性社員が現場で働きやすくなったこともあり、今では従業員30名まで成長を遂げた例もある。
KOMTRAXで建機のIoT化、スマートコンストラクションで建設現場全体のIoT化を進めてきたコマツは、さらに一歩進んで顧客に新たな価値を提供する取り組みをも行なっている。2017年10月からサービスを開始した「LANDLOG」だ。これは土木建設業界全体に衝撃を与えた。
顧客利益のために、プラットフォームをオープン化
「3次元データで現場の可視化をする場合、そこにはコマツのICT建機以外にも、他社製の建機も存在します。そうした建機のデータも踏まえて見える化しなければ、本当の意味でのすべての現場の可視化にはならないし、真のお客さまの利益追求にも至らない。そう考え、各種機材からモノ・コトのデータを吸い上げるプラットフォームであるKomConnectを切り離し、どの企業でも使えるオープンプラットフォームとして提供することにしました。狙いは、現場の全工程を3次元データでつなぐこと。お客さまの課題解決を進めるには、自社で囲い込むのではなく、広くパートナーとつながるほうがゴールへの到達は早いと考えています」
四家氏はこう語るが、相当に思い切った決断である。プラットフォーム上にはコマツだけでなく競合企業の建機のデータもアップロードされ、それを競合企業がアプリケーション提供に使えるのだ。それでもLANDLOGを提供するのは、「お客さまの利益につながるなら競争があるべき」と考えるため。スマートコンストラクションと利害が衝突する面もあり、社内には異論も多かったがトップの決断で実現したという。
「お客さまが望む課題解決のゴールはどこなのか?を起点に発想する文化がコマツにはもともと根づいていたと思います。お客さまの予想を超えて『ワオ!』と驚き、よろこんでもらえるサービス、ソリューションを提供するのが私たちの務め。今後もその姿勢は変わりません」

日本発の「製造業+IoT」で世界展開を目指す
製造業がIoT化を進める際のポイントを四家氏に聞くと「オープン化」、そして「スピード」という答えが返ってきた。現場をつなぐために必要なのは、建機の情報を含めたオープン化。また、顧客の課題解決につながるなら、失敗を恐れず「朝令朝改」のスピードで決断しなければいけないという。そして高速でPDCAをまわす。今後、スマートコンストラクションは海外展開を視野に入れているが、日本発の取り組みがどこまで受け入れられるのか。引き続き注目していきたい。